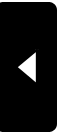保険販促委員会 Ver.どすごいブログ › 2013年01月
2013年01月17日
直木賞 『 等伯 』
きょうで、阪神・淡路大震災から18年が経過しました。
保険業界に飛び込んでから数ヶ月での出来事でしたので、
その日イチニチの記憶は鮮明に残っております。
さて、昨日は芥川賞と直木賞の発表がありました。
そのなかでも、芥川賞には史上最年長となる75歳 黒田夏子さんの「abさんご」、
そして、直木賞では戦後最年少となる23歳 朝井リョウさんの「何者」のお二方が注目を浴びていました。
私としましては、もう一人の直木賞を受賞した安部龍太郎さん(57)の「等伯」に目が止まりました。
というのもこの作品、安土桃山時代から江戸時代初期に活躍した絵師 『 長谷川等伯 』 が題材となった
歴史小説で、2年半ほど前に開催された 「 長谷川等伯 」 展 を京都国立博物館へ観に行った時には、
とても感銘を受けて帰って来たからです。
ぜひとも、読んでみたい歴史ものです。
↓↓↓ ↓↓↓


2013年01月13日
本宮山登山 Vol.35

本日もこれから山頂を目指し登ってまいります。
果たしてきょうは富士山、見られるだろうか…?
追記 …
6時57分53秒・・・登山口付近の日の出 時刻です。
この時間合わせて登頂します。

太陽が徐々に昇りはじめ、木々のあいだから日が差し込むさまは、とても綺麗です。


この日はどうも体が重く感じ、ちょっとしんどく感じました。
身体がだんだんと暑くなってくるため着ているジャンパーを脱ぎコシに巻きます。
背中に汗をかいているのが分かります。
しかし、ちょっと風が吹くと寒さを感じ、暑いのか寒いのか分からなくなりそうです。
なんとか無事に登り終え、拝殿にてお参りを済ませます。
この日の気温は2度。 平地は6,7度といったところでしょうか・・


この日も残念ながら富士山は見えませんでした。

そして近ごろマイブームはコレ・・・ 冷めた身体を温めます。

樹齢1000年の御神木であるスギの高さは30m。

しばし休憩のあとは下山です。
【 馬背岩 】 ↓ ↓ ↓

途中、第二東名が真下に通るであろう場所へと。
画像の中央にトンネルが見えるのが分かるでしょうか・・?

登るとにはすれ違う人は数人ですが、下山時はかなりの人とすれ違います。
100人近くの人とすれ違っているかも。。
出会う人、出会う人に 「 おはようございます 」 と挨拶します。
なかには無言の人も・・・きっと声を出すのもが もしんどい のかもしれません。

なにはともあれ、この日も無事に登頂、そして下山できました。
ありがとうございました。
そして、汗を流すために・・・ 続きを読む
2013年01月11日
両党です
近ごろ、めっきりビール党になってしまいました。
かつては、苦手な飲みモノのひとつだったのですが…
それがいまでは、どちらにしようかと迷うほどの変わりよう。
人は変わればかわるものですね(笑)

そうかと思えば、鏡開きにはご覧のとおり…
火にあぶったお餅が入った おしるこ は、香ばしくておいしい。
もちろん塩加減が大切なのは言うまでもありませんが…
塩昆布がコレまた甘味に合ってます。


そしてまた こよいも ビールのおいしさを堪能したいと思います。
かつては、苦手な飲みモノのひとつだったのですが…
それがいまでは、どちらにしようかと迷うほどの変わりよう。
人は変わればかわるものですね(笑)

そうかと思えば、鏡開きにはご覧のとおり…
火にあぶったお餅が入った おしるこ は、香ばしくておいしい。
もちろん塩加減が大切なのは言うまでもありませんが…
塩昆布がコレまた甘味に合ってます。


そしてまた こよいも ビールのおいしさを堪能したいと思います。
2013年01月09日
真心を頂戴する

新年が明け、はやくも松の内(7日)も過ぎました。(もともとは15日)
年賀状は、松の内までの良いとされる場合や、15日まで良いとされる場合など
地域によっても様々です。
年賀状を出し忘れたときや、ご返事が遅くなってしまった時など、または年賀状をもらいながらも、
喪中であるためお出しすることが叶わない場合など、『 寒中お見舞い 』 としてお出しする方法も
ありますね。
寒の入り(小寒)から、もしくは松が明けた頃から、立春の前日までが「寒(かん)」の時期なので、
この期間でお出しするのがよいと思います。
ちなみに立春から2月下旬ころまでは、『余寒お見舞い』です。
さて話はかわって、常々つぎのように思っていることがあります。
“ 人様へ祈念をこめて、御守りをお贈りする ” ということ。
お客様で事故の多かった方には安全祈願の御守り、ご懐妊されたと聞けば安産祈願の御守り、
などなど・・・
しかし残念ながら、そうは考えながらも、ほとんど実行できずにいました。
そのような中で、実はこのたび、私自身が御守りを頂戴する機会に恵まれました。
「 まごころ 」 とはこういったことを言うのだと、感動した瞬間でした。

このような御守りは、下記のような御守袋に入れて大切にしたいものです。
↓ クリック ↓

「自分がして欲しいと思うことを相手にしてさしあげる」 ⇒ 『金の法則』
「自分がして欲しくないと思うことは相手にはしない」 ⇒ 『銀の法則』
これまで私の基本方針としては、『銀の法則』でしたが、
ときには『金の法則』も大切であると思った瞬間でした。
ありがとうございました! 続きを読む
2013年01月04日
仕事始め ~ 砥鹿神社 里宮

本日から仕事始め。
さっそく、保険会社二社へ初荷と御年賀を持って、新年のご挨拶。
その帰りの光景…
今日はとても空気が澄んでいたため、はるか彼方に雪化粧した南アルプスの山々が見られました。
場所によっては富士山も見えたらしい。
そして午後からはこちら。

毎年恒例、一宮町にある 三河国 一之宮 『 砥鹿神社 』 へ参拝。

昨日の本宮山 山頂にある奥宮につづいて本日は里宮へ。


きょうは、意外にも空いていました。

御参りができると、不思議と安心できます。

タグ :砥鹿神社
2013年01月03日
本宮山登山 Vol.34

本年度、砥鹿神社奥宮への参拝も兼ね、初の本宮山へ。
前回は12月30日にいって参りました。 ⇒ ☆
この日のスタートは日の出時刻より少し早い、6時46分。
登っている最中に山間から陽がさしてきました。

ここは21丁目の最初の急勾配の場所。
一見、難所のようにも見えますが、手すりがあるのでそれほどでもありません。

昨年末に遭遇した上半身スッポンポンのおじさんとまたもやすれ違いざまに遭遇。
きょうは寒かったためウインドブレーカーを羽織っていましたが、前はハダケテ
その下は、やはりスッポンポン(笑)
岩場を手を使わずよじ登ります。
41丁目を過ぎたあたりにある水飲み場。2009年の台風では屋根が崩壊してしまいました。
これを超えると神域に入っていくため、ここで手を洗い、口をすすぎ、清めます。
ここを超えれば、あとひと踏ん張り。

やっとのことで奥宮へ上がる石段です。

これが本年の初詣と相成りました。

奥宮の気温計は氷点下3.5度。

富士山を拝められるかと思い、さっそうと足を運べば・・・

かすかに見えるような見えないような。。。

しばし休憩・・ やはりここでは温かい おしるこ ですね。

下山途中、ペッツボトル水が凍っているのにはビックリでした。


下山後はやはり温泉。
登山口 スグそばにある「本宮の湯」へ。
昨年12月リニューアルしました。
開店と同時にすごい人。
湯船は満員。でもここは強引に割り込み湯船の真ん中を陣取ります。
元来、小心者が故に勇気のいる行動でしたが・・・(笑)

ちなみこの画像はイメージです。
けっして混浴ではございませんのであしからず。。(^_^;)
 続きを読む
続きを読む2013年01月02日
天皇陛下の御言葉
本日、皇居での一般参賀をテレビで観ていた時、たいへん興味深い場面に遭遇しました。
それは国民に向けられた陛下の御言葉のなかの一句。
『 本年が国民一人びとりにとり… 』。
“ 一人ひとり ” ではなく、 “ 一人びとり ” なのだと。。
新年からあらたに一つ物事を学びました。
ありがとうございます!
タグ :ブログ開設三周年
2013年01月01日
年賀状 2013
新年 あけまして おめでとうございます。
旧年中はお世話になりありがとうございました。
本年も引き続き、どうかよろしくお願い申し上げます。
さて、新年はじめの記事は、手紙・ハガキ好きらしく、 「 年賀はがき 」 について。
みなさまのお手元に届いた年賀状(喪中の方はすみません)、はがき表面は
どのような切手柄が描かれていたでしょうか・・・
その絵柄に隠された秘密があるのは、ご存知でしたか?
ことしの 「 年賀はがき 」 には、三つの絵柄に、あるものが隠されています。
まずは一つ目・・

おせち料理の切手柄の下に注目。 “ 年賀 ” と押印されたところには縦線が描かれていますが、
日本だけ太いのが分かるでしょうか? (矢印部分)
これ、お箸の模様なんですよ。 上におせち料理の絵柄、そして下にはお箸の絵柄。
二つ目は、

くまのプーさんの絵柄のなかにハートマークがありますね。
そのなかにプーさんの絵柄があるのが分かるでしょうか?
(ほかにも隠れていますので探してみてください)
そして三つ目、

ピーターパンが持つスティックからハートがいっぱい放たれていますがね。
そのなかに、ミッキーマウスの姿を見つけられるでしょうか?
(ほかにも隠れミッキーがいますよ)
郵便事業も民営化になってから、なかなか心くすぐることをやりますね。
教えてもらった記事は、師匠のこちらから ⇒ ☆
タグ :年賀状